導入事例・コラムCOLUMN
「名プレイヤー、名監督にあらず」の正体とは? ~マネジメントへの役割転換メカニズムを考察する~

どれだけ素晴らしい業績を上げたプレイヤーであっても、マネジメント職に就いた途端に精彩に欠けてしまう...。そんな様子に、心当たりがある方は多いのではないのでしょうか。
組織の一員として生き生き働くうえで、注目したいキーワードが「役割」です。ただし役割は目に見えるものではないので、本人も周囲も分からないまま社会人生活を送っていることも少なくはありません。
下手をすると見えない役割の存在があることで、本人が果たしたい役割と周囲が期待する役割がズレてしまっている状況も散見されます。
本記事では、そのような役割ギャップが表れやすく、かつ企業に大きな影響を与えるマネジメント場面に焦点を当てます。「なんでプレイヤーとしてはあれほど優秀だったのに、マネジメントになった途端に活気を失ったのだろう?」という現象が思い当たる方は、参考にしていただければ幸いです。
企業で働く以上は求められる「役割」
最初に、ビジネスパーソンであれば頻繁に耳にする「役割」について考えていきます。
管理職に限らず、社内でやや伸び悩んでいる方がいる場合は、役割に起因している可能性があるかもしれません。
組織での役割とは
企業で働いている以上、すべからく社員には役割があるということに異論を唱える方はいないでしょう。
ところが、成果が出にくい組織においては、この「役割」の概念が当たり前のものとして捉えられていないことが多いのです。役割が曖昧になっていると、役割から逸脱した言動があったとしても、本人も周囲も気がつきません。
例えば、リーダーが困っているメンバーに手を差し伸べなかったとしても、本人も周囲も違和感を覚えないようなケースが挙げられます。
少し視点を変えて、「組織」と「集団」の違いを役割観点で考えてみます。
「組織」とは、「共通の目的」があり、さらに個々の構成員の「役割や機能」がはっきりとしている「集団」です。
極端な見方をすると、組織は役割を持った人の集まりですが、集団としてあるだけでは、不特定多数の人たちが集まった状態といえます。
つまり、組織が有機的に機能するためには「社内にはどんな役割があるのか」が明らかになり、「一人ひとりが自分の役割を認識している」状態であるべきでしょう。
組織での役割転換は「トランジション」が重要
究極的には社員一人ひとりに求められる役割は異なりますが、多くの企業では組織のなかでの相対的な立ち位置によって、共通して求められる役割もあります。
弊社では多くの企業で共通する「10の役割」を設定し、「トランジション・デザイン・モデル」と称しています。
<図表1>組織における期待役割ー10のステージ
参考:成長につながる"トランジション"をデザインする
トランジション(transition)とは、「移行」「変化」「過度」などの意味を持ち、一般的には動画制作で、前後のカットを自然につなぎ合わせるために使われる効果(エフェクト)のことです。
一方、ビジネスにおいては、配置転換や人事異動など、ある段階から次の段階へと移行する時期を意味する言葉として使用されます。
人事領域においては、主にキャリア発達の過程で注目されています。
トランジションは、人に大きな変化をもたらす重大な局面(クライシス)であると同時に、それまでの経験を見直し、新しい選択肢や変化をもたらす転機ともいえるでしょう。
「トランジション・デザイン・モデル」は、企業における役割転換の際、早期から計画的に対応を行うことで、求める役割に対して本人が適応困難となる状況を回避する目的があります。
役割転換にともなう本人のギャップを取り除くだけではなく、新たな役割のもと早期の成果獲得にもつなげられます。
マネジメントへの役割転換の実態
トランジションには「学生から社会人への転換」や「役職担当後のプロフェッショナル転換」など、いくつかの象徴的なステージがあります。
とりわけ、ステージ転換に困難を要するのが「マネジメント層への役割転換」でしょう。
弊社の調査では、「新任マネージャーの5人に1人は、マネージャーに適応できていない」ということが判明しています。
「今振り返ると、管理職に就任後の新しい環境への適応は、どの程度うまくいったと思いますか」という質問に対して、「適応が(どちらかといえば/まったく)うまくいかなかった」と答えた人が、20.1%いました。
<図表2>マネジメントへの適応状況(定量調査(1)・定性調査(2))
参考:新任マネージャーのほとんどが トランジションに苦労している
マネージャーは「集団に働きかけて、組織業績を達成するとともに変革を実現する」ことが求められている役割ステージです。
この役割ステージのトランジションを乗り越えたサインは、「メンバーに任せることの効果、そして仕事の打ち手と職場のつながりを実感すること」になります。
一方で、乗り越えられない場合にも何らかのサイン・症状が表れます。
例えばマネージャーがメンバーの仕事を奪ってしまったり、メンバーにやらされ感が広まってしまったりして、組織力が大きく低下するというような症状です。
それを未然に防ぐためにも、下図のような意識・行動を早期に身につけさせていくことが必要です。特にマネージャークラスになると、周囲からのフィードバックや過去の失敗体験を取り込んで、早期に行動改善することがトランジションにはより効果があります。
<図表3>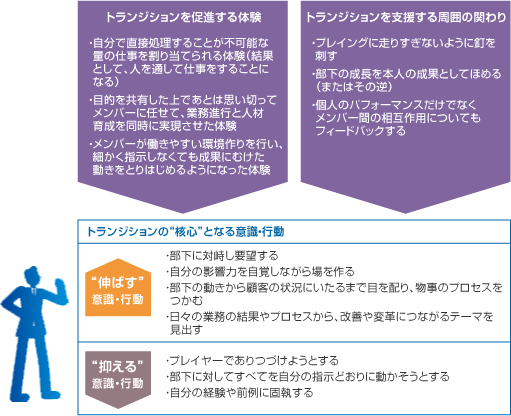
参考:企業人の成長をデザインする
このようなモデルをもとに「マネージャーの役割としての経験を積ませる」ことを意識することがお薦めでしょう。
スムーズな立ち上がりには「資質」に注目すべき
ここまでの調査からの考察で、マネージャーのトランジションには「役割転換する経験」が重要だと分かってきました。
ただし、ビジネス環境は必ずしも社内の管理職育成に有利に働くとは限りません。むしろ、育成観点に絞った場合、コントロールできない経験が多くなりがちなのも事実です。
そこであらためて着目したいのが、偶発的な「経験」ではなく先天的な「資質」です。
本コラムのタイトルで示したとおり「名プレイヤー=名監督」の法則が成り立たないケースの多くは、管理職の資質・適性を無視して「これまでのプレイヤーの実績」のみで管理職を抜擢している傾向にあります。
例えば、周囲の動きにはあまり関心がないものの、自分で精力的に動いて成果を出すことに長けている方がいるとしましょう。
そのようなスタイルを得意とする社員が、他者であるメンバーの持ち味を引き出しながら組織成果を出すマネジメントを求められたら、どうなるでしょうか。
もちろん本人の努力や育成効果で変化することもあるかと思いますが、利き手以外を鍛えるのは時間がかかるうえに、本人に苦痛が伴うことも少なくありません。
弊社の「管理者適性検査NMAT」は、職種や過去の実績・成果に関係なく「管理職として適性があるかどうか」や「どのような管理職タイプとして活躍できるか」という資質を測定しています。
<図表4>企業の成果創出モデル
参考:「なぜあの人がマネジャーに?」という問いに答えられる 将来の活躍が期待できるマネジャーを選ぶためのヒント
この「資質」や「適性」という観点は、実は社内の人間の目だけでは見抜けないことが多いものです。
適性検査は、新卒採用では「ポテンシャル採用」の言葉のもとに、活用されている傾向にあります。実は同様に、よく分かっている「つもり」の既存社員の管理職としてのポテンシャル把握でも、適性検査は効力を発揮します。
むしろ、仕事に一定年数十字してきたマネジメント候補であれば、人事や本人も「自分の得意・不得意」を勘違いし、無理をしているケースも実は少なくありません。
そのような「変化しにくい強み・弱み」を、昇格要素として「これまでのプレイヤー実績」に加えるだけで、スムーズに立ち上がるマネジメント層の増加が期待できるでしょう。
適性検査は「3カ月の壁」を乗り超えるサポートになる
マネージャーへのトランジションについて、もう1つ考慮すべき観点は「時期」です。
具体的には、特に注視したいのが着任直後の3カ月~6カ月です。
この「管理職の仕事が分かるまでの期間」は、半年未満が40.5%、1年未満が64.6%、2年未満が80.6%となっています。
<図表5>管理職(課長)の仕事がわかるまでの期間(定量調査(1))
参考:新任マネージャーのほとんどが トランジションに苦労している
また、定性調査では、8人中6人が、着任3カ月後に壁にぶつかっており、6カ月後には何らかの形で壁を克服していました。
3か月に壁に当たった際、新任マネージャーはまだマネジメントの経験が乏しいため、乗り超えるための拠り所が少ない状態といえます。
こんな際、NMATの本人フィードバック用の報告書が活用できます。
NMATは「あなたのキャリア開発のために」「リーダーシップスタイル報告書」の2種類の本人向け報告書を用意しています。特に、後者の報告書では「マネジメントの壁」にフォーカスして本人の特性を解説しているので、壁の克服にお薦めです。
例えば「周囲を統率する」特徴があるマネジメントの場合、「熱くなりがちなので、メンバーの心情より自分の考えを訴えていないか、注意しましょう」のようなアドバイスも掲載されています。
さらに「同じ壁にぶつかった人の体験談」も掲載されているため、壁を乗り越える材料が少ない新任マネージャーには、参考になる情報のはずです。
特に就任3カ月~6カ月は忙しい時期なので、フォローのための集合型研修も難しいかと思います。
そんな際は本人にフィードバックするだけで、壁を乗り越えるサポートができるNMATは心強い存在になることでしょう。
「名プレイヤー」を埋もれさせないために
「営業」「デザイナー」「経理」「ITエンジニア」など、職種ごとに向き・不向きはあるでしょう。同様に、管理職という「役割」にも汎用的な適性があります。
特定の職種で能力を発揮して名プレイヤーとして活躍した方が、管理職になって同じように活躍できるとは限りません。
ただし名プレイヤーであったという実績は、もちろん管理職としても通用する可能性を秘めています。
仮にプレイヤーとしての実績だけで管理職に就任させてしまった場合でも、今後どのようなマネジメントスタイルで活躍していくかは本人次第です。
NMATをフィードバックすることであらためて「自分にはどのような資質があるのか」を本人は理解できます。そのワンクッションがあることで、プレイヤーとして発揮した力を「管理職という役割にどう転換・展開していけばいいのか」と、前向きに考えていけるのではないでしょうか。
