導入事例・コラムCOLUMN
Z世代を「異質」と捉えるか、「異能」と捉えるか- ~現代で求められる育成スタイルの変革とは~

「デジタルネイティブ世代」「タイパ重視世代」「ダイバーシティ世代」......など、
さまざまな特徴で表現される「Z世代」。
1990年代中盤から2000年代までに生まれたZ世代が、ここ数年で新入社員として入社してきたという企業も多いことでしょう。Z世代の価値観や言動に戸惑う方もいるかもしれませんが、遡れば「団塊の世代」「バブル世代」「氷河期世代」「ゆとり世代」など、時代の変遷とともにさまざまな「○○世代」は存在していました。
育った環境が異なれば「違い」が生じるのは、当たり前でしょう。それ自体は、可も不可もありません。
歴然たる事実として存在する「違い」を、どのように捉えるか-。本記事では、Z世代に代表される世代間ギャップを、組織力を向上させるためのマネジメントと捉え、その秘訣について取り上げます。
異質から学べばVUCAの時代を勝ち抜ける
先々が見通しにくいVUCAの時代では、組織の在り方はVUCAとWell-beingへの対応が急務となっています。
そのような環境変化にともない、企業内での風土や世界観も、かつての「組織中心の世界から「個と組織が生かし合う世界」への変革が求められています。
<図表1>求められる組織アップデートの方向性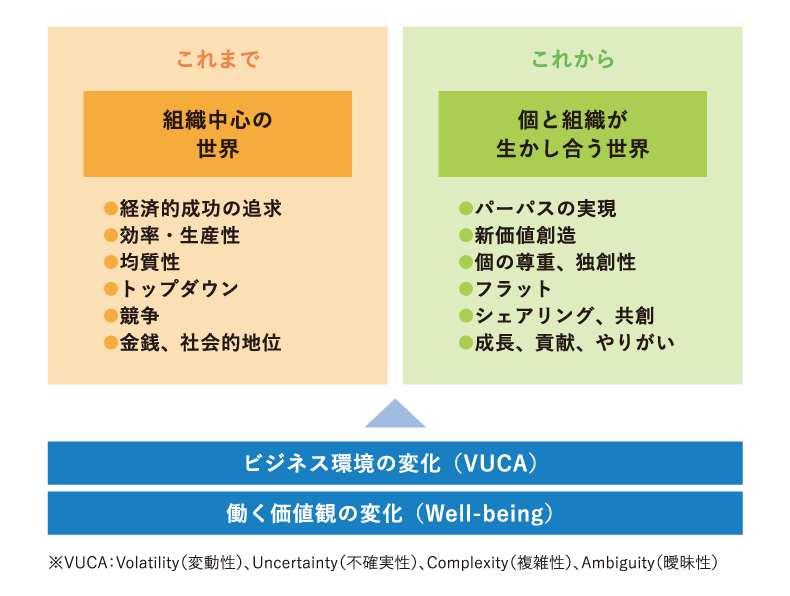
参考:Z世代と共に創る未来 ~異質さに学び組織をアップデートする
高度経済成長期に代表されるような、右肩上がりの経済成長が見込めた状況では、「組織中心の世界」の戦略が有効でした。すなわちトップダウンでの指示を、効率性や均質性を重視しながら、組織でまとまった動きを取ることです。
しかし正解がなく先も見えにくいVUCA時代のビジネス環境では、新価値創造(イノベーション)ができる組織へアップデートしていく必要があるでしょう。
イノベーションを起こすためには、働く価値観や仕事のやりがい・ライフ面も含めて、社員一人ひとりを大切にするWell-being意識が重要です。組織運営においては、多様性や個の尊重を通じてエンゲージメントを高めることが求められます。
例えば多様性の象徴となるのが、「Z世代」と括られる新入社員・若手社員世代でしょう。
今日の若者は、世界中の情報にアクセスできます。
SNSやインターネットに日常的に接し、最新の情報やさまざまな方法論についての情報を保持しているため、若者の方が詳しく優れている領域が生まれています。
ただし、現在の管理職層は組織中心の世界での成功体験で考えてしまいがちです。
そのため、個の尊重を通じて成果やエンゲージメントを高めるアプローチに、戸惑いや葛藤を感じながら試行錯誤されている声をよく聞きます。
変化の少ない平時では組織の同質性がプラスに働く一方で、現代では異質性が既存組織にない新しい視点・やり方をもたらす存在となります。変化が大きい環境では、異質なものに蓋をしたり排除したりすることなく、力を引き出すことで組織のアップデートにつなげることが重要です。
つまり、組織マネジメントにおいて重要なのは、「異質」を「理解できないもの」と認識するのではなく、「自分たちにはない異能」と捉えることでしょう。マネジメントの捉え方次第で、Z世代の存在はハレーションにもなりますし、新時代に向けての組織アップデートへのヒントにもなり得るのです。
Z世代が上司や職場に求めること
Z世代の力を、組織アップデートに活用するためには、まずは彼らが上司や職場に求めることを真摯に理解する必要があります。
以下の図表は、弊社で毎年実施している新入社員意識調査において、理想の職場・上司像の2013年と2023年の結果を比較したものです。
<図表2>Z世代の特徴
参考:新入社員意識調査2023(PDF)
かつて理想として挙げられたような「鍛え合う」「活気」「情熱」「厳しさ」のような要素は、2023年には総じて減っています。その一方で「個性の尊重」「助け合い」「丁寧な指導」「ほめる」のような要素を求める声は、増えている状況です。
この変化の背景として、Z世代は生まれたときからVUCA×Well-beingの環境で育った、いわば「新時代ネイティブ」であることが考えられます。
Z世代は、これまで成功をもたらした「組織中心の世界」の価値観や仕事の進め方には不慣れかもしれません。しかし、これから企業が対応を強化しようとしている環境にはむしろネイティブで、強みや生かせる価値観が備わっているといえます。
新価値創造においては、立場や経験に関係なく誰もが意見を言い、一人ひとりの強みや個性を発揮していくことが有効ですが、図表2で緑色部分に挙げた要素はそれらに近いでしょう。
また現代ならではのストレスが多いビジネス環境下では、お互いに助け合い、プラス面に目を向けてメンタルやモチベーションを高める方が、エンゲージメントやパフォーマンスにつながりやすいといえます。
伝統型から抜け出した育成スタイルへの変革
Z世代の育成現場では、「彼らは言われたことはやるが、自分で考え動くことは苦手」「失敗すると落ち込む」などの声がよく聞かれます。この背景には本人側の問題もある一方で、周囲の関わり方・育て方が自律学習を高めるものになっていない点も挙げられます。
伝統的な育成スタイルは、これまでの成功体験を伝承していくことや、叱咤などの厳しい指導によって反省で成長を促すことなどが特徴です。しかしこの方法は、個の尊重や内発的な動機を重視するZ世代にはフィットしないケースが多いでしょう。
そこで、Z世代の特徴をふまえた育成スタイルが新たに模索され、成果を上げ始めているのです。
<図表3>新たに加えたい育成スタイル
参考:RMS Message vol.73 [2024年2月]
これらの育成スタイルは、実はZ世代だから有効というよりも、人の自発性を引き出し、エンゲージメントを高める原理原則に近いものです。例えば、否定せずに安心と信頼で自律を引き出す方法は、「心理的安全性」があるとして、Google社をはじめ世界の多くの組織で、エンゲージメントやパフォーマンスを上げる成果が報告されています。
また、一人ひとりの個性や多様性を尊重し自己決定を支援していく方法は、内発的動機づけや自己決定理論( Deci & Ryan, 1985)として、自律や創造性を引き出すメソッドの原点となっているものです。
正解がなく不確実性の高いVUCA環境のなかで生まれ育ったZ世代に対しては、組織中心の伝統的な育成スタイルのみで接するには限界があります。
すなわち、マネジメントにはZ世代への傾聴や問いかけを通じて、心理的安全性や自己決定の重要さを伝えるスタイルへの変換が求められているといえるでしょう。
現管理職層は新時代の育成に対応できるのか?
これまで、Z世代の力を引き出し、組織アップデートにつなげる道筋についてお伝えしてきました。ここからは、現管理職層に対するアプローチについて紹介していきます。
第一歩として、新しい育成スタイルへの適応性を確認するためにも、現管理職の現状を把握する必要があります。
現状把握には、客観的に人物特性をつかむことができる適性検査を活用すると良いでしょう。
管理職に特化した適性検査のパイオニアである「管理者適性検査NMAT」を活用したアプローチ例を2つ紹介します
①現管理職層の分析
NMATでは、一律のマネジメントスタイルではなく4つの管理職のタイプを設定し、各々の「適性(向いているかどうか)」と「指向(やりたいかどうか)」を測定しています。
自社の現管理職が4つのタイプの「適性」「指向」にどのように分類されるかマトリクス分析をすることで、自社の管理職の特徴及び今後の新時代の育成スタイルに向けての強化ポイントが把握できます。
さらに精緻に分析を行いたい場合は、「Z世代のマネジメントがうまくいっている層」と「うまくいっていない層」に管理職を分類し、両グループでどのような違いがあるかを把握することも有効です。NMATでは「対人関係面」「課題解決面」を各々4つの尺度で測定しているため、合計8つの人物特徴から、違いをあぶり出すことができます。
この分析を通じて、「こういう人がZ世代のマネジメントが得意だろう」という一般論や想定論から、「自社の場合は、このような特徴がある人がZ世代のマネジメントがうまくいく」という、独自の気づきが得られるでしょう。
②管理職本人の自己理解の促進
前述の分析アプローチは、あくまで現状把握です。
したがって、今後の昇進・昇格基準には活用できても、現在の管理職層本人の自己理解の促進には活用しにくいといえます。
ただ、現管理職も自身の努力によって行動改善することは可能です。
NMATには、管理職本人が自己理解を深めるための「キャリア開発報告書」や「リーダーシップスタイル報告書」という、フィードバック専用の報告書もあります。
これら報告書には「強み」や「課題」を本人が理解しやすいように記述されているため、管理職本人も真摯に自分の特徴を見直せるはずです。
|
NMAT:本人用フィードバック報告書で分かること【例】 |
|
・自分がどの管理職タイプに向いていて、どのような啓発ポイントがあるのか |
Z世代へのマネジメントがうまくいっていないという管理職の方は、本人もそのままで良いと思っているわけではないでしょう。「何か変わるきっかけがほしい」と思っている管理職に、客観的なアドバイス情報を提供することで、変化の1歩目を踏み出す機会となるかもしれません。
まとめ:ORではなくANDで考える
異文化理解のフレームワークに「ホフステードの6次元モデル」というものがあります。
その6つの尺度に「不確実性の回避」があり、日本はこの尺度が世界で4番目に高いことが分かっています。
つまり、日本人は不確実で曖昧なことを嫌う特性があり、白黒をつけたがるのです。
企業内においても、不確実性を脅威と感じるため、取り除こうとしてルールや規則を作りたがります。また、正解を欲する傾向もあります。
そのため日本企業では「Z世代or昭和世代」「リモートワークor出社」や「正規社員or非正規社員」のような、「いずれか」で捉えがちです。異質なものを組織力向上に取り込むためには、OR(AかBか)ではなく、AND(AもBも)で捉えるスタンスが重要になります。
「AもBも」取り込もうという目線で課題を眺めることで、はじめてCやDという、これまで存在していなかった新たな選択肢が生まれることにつながるのです。
元来、人間は一人ひとり異なって当たり前です。
「Z世代」に代表されるような自分と違う特徴を持つ人材に遭遇したら、新たな何かを生み出すチャンスと捉え、思い込みを捨てて違いを味わってみるのはいかがでしょうか。
