導入事例・コラムCOLUMN
マネージャー候補は昇進・昇格時期に探し始めても遅い? ~早期キャリア開発こそがスムーズな管理職登用のカギ~

企業で働いて数年が経過したビジネスパーソンであれば、誰しも「自分は将来この会社でどんな立場になり、どんな貢献をすべきなのだろうか」と考えることでしょう。
現在は、一昔前のようなマネジメントのみの単線型人事制度でなく、複線型の人事制度を導入している企業も増えています。キャリアの選択肢が増えること自体は、働く社員にとって歓迎すべきことでしょう。
ただし一方で、「管理職の意向はあるものの、その選択肢が正しいのだろうか」「どのキャリアを歩むことが自分に向いているのか分からない」と、不安を抱える方も多いものです。特にプレイヤー時代の利き腕だけを判断材料にして、未経験の管理職としての向き・不向きを考えるのは、難度が高いといえるでしょう。
今回は、若手~中堅層に向けてのキャリア開発を進めることで、昇進・昇格にどのような影響があるかを考えていきます。
「管理職」は突然誕生するものではない
管理職は、一般社員とはかなり異なる存在です。一般社員は自業務の成果に責任を負いますが、管理職は自部署の部下メンバーが行う業務の進捗状況を把握し、チーム全体の成果管理をする役割を担います。
そのため、管理職は人事や予算などの「決裁権」を持ちながら、組織運営を行います。管轄部署の責任と権限の範囲内で、自ら判断を下すことが管理職の重要な役割です。
また、通常の管理職は労働基準法における「管理監督者」に該当するため、休日や労働時間に関する規定が適用されません。法律での時間外労働の上限を超えて働くことはできますが、休日手当や残業代などの支給がない点も一般社員との違いです。
参考:労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために【厚生労働省】
当たり前ですが、管理職には誰しも、一般社員の時代を経てから就任します。
自業務成果だけに集中している視界しか持たない一般社員が、昇進昇格制度によって「来期からあなたは管理職です」と言われても、突然管理職としてのマインドセットができるわけではありません。
昇進昇格は「半年に1回」など時期が決まっているケースが大半なので、その時期にさしかかって候補者を探し始める企業も少なくありません。
そのようなケースでは、対象者は「心の準備ができていない」状態で管理職を任されることになります。
もちろん管理職就任後に新任管理職研修などを行うことで、徐々に管理職としての視界やスキルを開発する方法も有効です。ただし、管理職就任前から候補者がある程度管理職になる心構えをしている方が、就任後の育成施策の吸収スピードが速いのはいうまでもないでしょう。
中堅社員時代の経験は重要な意味を持つ
管理職に就任したからといって管理職としてのスキルを持った社員が誕生するわけではないのであれば、企業に勤めるうえで、いつ頃から何をしたらいいのでしょうか。
そこで注目したいのが「中堅社員層」です。昨今は、各社から「管理職になりたがる中堅社員が減っている」「中堅社員の離職が目立つ」など、この層に関して苦慮している声も聞かれます。
ただし「中堅社員」といっても、年齢、職種、職級などの属性、経験や志向などの個別性ゆえに一括りにしにくい特徴があります。その影響で、会社の階層別教育でも中堅社員への対応は手薄になりがちで、この層は打ち手を施されていないケースも多いようです。
一方で、管理職を起点とした研究で松尾(2013)は、成果を上げる管理職には「部門連携・部下育成・変革参加」の経験が重要であることを説いています。
加えて、中堅社員を含む管理職以前に有効な経験を積むことの重要性も指摘されています。経験からの学習には「過去にどのような経験をしているかによって、現在の経験が規定される傾向」(経路依存性)があることも報告されているのです。
実際に、中堅社員の時点で成長を感じた経験(以下「成長経験」)とはどのようなものなのでしょうか。
弊社が行った調査では、成長経験の1位は「モチベーションの維持が難しい環境下で耐えきる」でした。困難な状況でも、果たすべき役割や業務を責任を持ってやり抜くことを成長経験として認知しています。業務の内容や進め方、仕事環境、人間関係などモチベーションの変数は複数考えられますが、自分で何らかの耐える意味や理由を見つけながらモチベーションのバランスを取って仕事を進めていることが想像できます。
続いて「2.多様な価値観の人と仕事をする」「3.自分なりの問題意識に基づき目標を定め、行動する」と、協働や問題解決の経験が続きます。
参考:『RMS Message74』
管理職に限らずですが、ビジネスパーソンは誰しも「過去の経験」をもとにしながら、未知の業務に挑戦していきます。
もし中堅社員時代に意識的に成長経験を積めれば、管理職として活躍する礎を築くことができるでしょう。
中堅社員本人の自覚・自我をどう芽生えさせるか
前章で紹介したような「仕事を通じた成長経験」を中堅社員に積ませることは望ましいですが、現実的にはちょうどよい仕事があるとは限りません。
次に注目したいのが中堅社員の「志向」面です。同調査でキャリア開発志向や管理職志向についての回答を見ると、「キャリアを開発するためであれば今の会社にこだわらない」について、「ややあてはまる」「とてもあてはまる」は37.0%、「どちらともいえない」が36.0%でした。
「今の会社でキャリアを開発していきたい」については、「ややあてはまらない」「全くあてはまらない」は35.7%で、「どちらともいえない」が39.8%でした。
この結果からは、中堅社員は自身のキャリア開発について、属する会社に限定せず、柔軟で自律的なキャリア形成を意識していることがうかがえます。
また、管理職に「なりたくない」「どちらかといえばなりたくない」と回答した割合は約半数の50.8%であったことからも、管理職昇進については積極層が必ずしも多いとはいえない結果となっています。
参考:『RMS Message74』
しかし、弊誌vol.42 特集1「伝えたい マネージャーの醍醐味」では「昇進前に、管理職になりたくなかった人(ネガティブ群)のうち、半数以上が昇進後にその気持ちがポジティブに変化していることが確認」されています。
したがって、中堅社員時代には管理職志向がないことそのものを問題視するのではなく、本人の志向や意識にアプローチすることが重要といえます。
つまり、管理職志向は次のステージへの必要条件でなく、もとより弾力的であると捉え、イメージ形成や経験を通して、志向も徐々にトランジションしていくものだと考えるのです。柔軟で弾力的なキャリア志向があるという前提のもと、前述したような成長経験を段階的に積めるステップや、本人が実務から少し目線を外し、本来的に自分が進むべきキャリアのイメージを描くステップが求められるでしょう。
自覚を誘発させるための客観情報
本人の志向や意識にアプローチするといっても、何も材料がない状況で「管理職になりたいか?」と聞くだけでは、中堅社員の内省を効果的に促せません。
ここで本人に自分を見つめ直す材料となるのが、客観的な適性検査の情報です。弊社の「管理者適性検査NMAT」では、全国の1200社・40000名と比較して、対象者の管理職としての適性や志向を測定しています。
適性検査と聞くと「昇進・昇格試験で使うもの」という印象を持たれる方も多いかもしれません。もちろん昇進・昇格審査での活用も多いのですが、昨今のトレンドとしては管理職になる前の中堅社員層に、自身のキャリアを考えてもらうための情報提供としての活用が増加しています。
例えば「管理職」と聞くと、画一的な印象を持ってしまう中堅社員もいるでしょう。しかし、プレイヤー時代の得手・不得手と同様に、現実の管理職は各々異なる持ち味を発揮しながら、マネジメントを進めています。NMATでは管理職を4つのタイプで定義しているため、タイプごとにどのようなマネジメントスタイルに適しているかまで、把握可能です。
「深い思考や専門性を発揮するスタイル」や「着実に業務を遂行するスタイル」など、管理職タイプのメッシュを細かくすることで、自分の動きをトレースしやすくなります。
さらにキャリア開発で注目したいのは、NMATは本人に結果をフィードバックするための専用報告書が2種類ある点です。
中堅社員クラスになると、会社の戦力として1人で仕事を進められる方が多いかと思います。だからこそ、目の前の現業務を通じて「自分の持ち味や強みはこれだろう」と勘違いしている方も実は多いものです。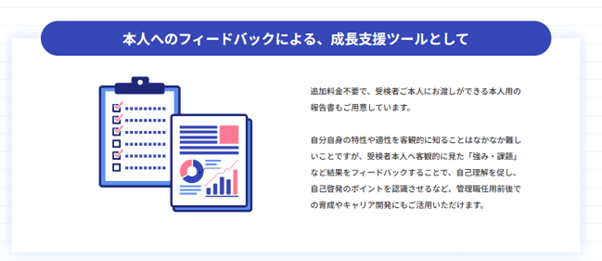
そのため、変化しにくい自身の本来的な性格特性を知ることで、「本当はどんな風に活躍したいのか」と、キャリアについて深い内省を導くことができます。
前述したように、中堅社員は対象者が多く、置かれた状況がさまざまです。
大がかりな研修実施などは躊躇してしまい、その結果何も手が打てない状況になることも少なくありません。
その点、NMATは1名あたり6000円・最短75分で受検できるため、研修と比べてコストやパワーを抑えることができます。結果のフィードバックについても、読み取り資料とともに、メールやタレントマネジメントシステムで伝えられるため、中堅社員の業務を阻害しません。
もちろん、結果をもとに上司との面談やフィードバックガイダンス・ワークショップの機会を設けると、よりキャリアを描きやすくなるでしょう。
中堅社員が生きると会社が生きる
「中堅」というポジションは、剣道の団体戦でいうと、5人のなかで3人目に該当します。例えば先鋒・次鋒という初手2人が勝っていたら、中堅が勝てばチームは勝利します。逆に初手2人が負けていたら、中堅が負ければ試合は負けで終了します。企業に置き換えても、中堅社員は企業の未来を左右する重要な位置にあると見なせるのではないでしょうか。
それにもかかわらず、中堅社員層は対象が広すぎて課題特定の難度が高いため、新入社員や管理職と比較すると、人材開発の優先順位が低い企業が多いようです。
そのため、中堅社員自身も目の前の仕事に必死になってしまい、管理職をはじめとした中長期のキャリア形成に目を向ける機会が少なくなっています。
一方で経営・人事の観点からすると、この中堅社員層から将来自社の成長を牽引する管理職を見つけなくてはならないという課題もあります。
「自分のキャリアが見えない中堅社員層」と「管理職候補を見つけたい経営・人事層」という双方の懸け橋となるべく、適性検査を活用してみてはいかがでしょうか。
